長男3歳、長女11ヵ月。
10か月間の育児休暇をあけて訪問看護師が今年1月から仕事復帰しました。
 (写真:療養通所介護まことの2階にある保育室前にて)
(写真:療養通所介護まことの2階にある保育室前にて)
育休中はずっと自宅での生活だったけれど、今は保育室に預けながらの仕事復帰をすることができ生活にメリハリがつけられるように。毎日あっというまに過ぎてしまいますが、日中離れているぶん子育てや仕事を頑張ることができていると教えてくれました。
コロナ禍での復帰に迷いや不安も多かったかと思いますが、今日はそんな育児奮闘中の看護師に復帰後の1日のスケジュールを聞いてみました!
『一日のスケジュール』
6:30 起床 家を出る8時までの間、朝ごはん、着替えなどやることが今までの2倍でバタバタ大忙し!!
長男も少しお兄さんにはなったけれど、気分次第で一人でできるときとできないときが。
(決まった時間に出発できるようにコントロールするのって本当に大変ですよね!)
8:00 出発 長男を認可保育園へ。長女は同法人内にある保育室わかばへ自転車を走らせます。
保育室へ預け始めた2週間は慣れない環境にギャン泣き・・・でしたが、今では慣れた保育士さんであれば
ハイハイしていってくれるようになったので気分も楽に。(初めての母子分離、ままも長女ちゃんもがんばりました!)
8:45 出勤 訪問 午前2件、午後2件 訪問後、記録や書類整理
17:00 お迎え 仕事を終え、保育室、保育園に自転車でお迎え。
17:30 帰宅 夕飯の準備、夕飯、入浴、入浴後に洗濯をする
21:00 就寝 子どもたちの寝かしつけをしながら一緒に就寝。。
『背景にある職場環境』
☑アピールポイント
【川崎大師訪問看護ステーション】
★管理者も子育て経験者なので理解がある
★川崎大師訪問看護ステーションでは、一日の訪問件数のノルマがない!
★記録や書類整理の時間も確保できるようにスケジュールを組み立ててくれる
★子どもの熱など急に休まなければならない場合に柔軟に対応してもらえる
★行事などの希望休みは100%叶えられるように組み立ててくれる
★ワークライフバランスを気にかけてもらえる
★スキルアップのための研修情報が盛りだくさん(情報のアップデートをしたい方も安心)
→→→安心して働ける!!!
【保育室】
★福利厚生の一つとして良心的な利用料金で預けることができる
★出産後の復帰時期を保育園の合否を気にせずに決められる
→→→ワークライフバランスを考えながらキャリアプランを立てやすい!!!
看護師Tさん、子育てと仕事の両立をしながら頑張っている姿をありがとうございました!








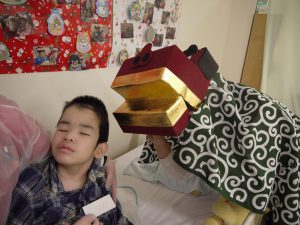







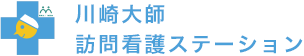


 (写真:療養通所介護まことの2階にある保育室前にて)
(写真:療養通所介護まことの2階にある保育室前にて)




